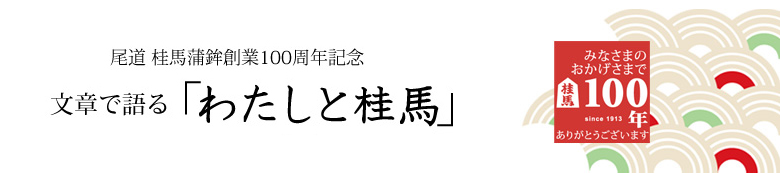|
ボクが生まれたのは、桂馬の斜め向いにかつてあった電気屋でした。けれども、中学から家を離れて遠くの学校に進学したため、尾道に住んだのは土堂小学校卒業まででした。
そのため、ボクの思い出にある桂馬は、初代の桂造さん時代のものです。桂造さんは小さい体なのに相撲が大好き、
とりわけ千代の山のファンで、尾道巡業があった時に関取を招かれ、私が店先で抱っこされた写真がありました。
当時桂馬の隣にあった毎日新聞社のカメラマンが写してくれたのでしょう。しっかりしたプロの写真でした。
海岸通りにある今の桂馬の駐車場は、かつては魚市場でした。当時はまだ珍しかったコンクリートの濡れた床に、裸電球に照らされた
いろいろな魚が並んで、なんともいえぬ面白さと怖さにワクワクして見に行ったものです。
そんな早朝なのに、桂馬の仕事場では桂造さんが長靴にエプロンで働いていらっしゃいました。
市場から石畳の坂を引きづられてきたトロ箱には、恐ろしい顔をしたキラキラした長い魚が、氷漬けにされて積まれていました。
「美形の魚は店で売られ、そうでない魚は夜明け前にこういうところに運ばれて、姿がわからないように加工されてから
売られるのだ」と子ども心なりに悟ったものです。
わが家にとって桂馬は、歩いて10歩のファーストフード店でした。
あの頃は、桂馬では、できたての熱いままでも売っていました。母はできたての時間にあわせて買いに行き、「熱いからね」と言いながら、
油が染みた所がまだらに透明になった紙袋のまま与えてくれました。
だから、ご飯のおかずというよりも、ドーナツかハンバーガーかコロッケのような感覚でしょうか。
私は梅焼きと小丸が今でも好きですが、その原因は、離乳食として食べたからかもしれません。それくらい、物心つく以前から食べていたような気がします。
ご進物用の木箱にきれいに詰まり包装紙に包まれたものが、桂馬の主力商品と知ったのは、大きくなってからです。
あの頃の柿天のへたは本物のへたを使っていましたが、なかなか入手しにくくなり、父の実家がかつて柿渋の製造をしていたことがあったので、相談を受けたこともありました。
桂造さんは従業員のために卓球台を置き、使わない時には私たちにも開放してくださったため、父と遊んだことがあります。
それが、父との貴重な思い出になり感謝しています。
銀座の「みゆき画廊」で毎秋個展を続けていますが、4年前、長女の優美さんが来場されて、そこから桂馬さんとの縁が
半世紀ぶりに復活し、私の絵の生徒Eさんが専務の芳子さんの高校時代の友人であったりして、ますます仲良しになってきました。
ちなみに、社長の村上ひろし(博志)さんの父上はきよし(清)さん、奥さんのよしこ(芳子)さんの妹はけいこ(啓子)さんですが、
私の本名は村上きよし(潔)で、兄はひろし(浩)、妹はけいこ(啓子)、家内はよしこ(佳子)というのは
、あまりにできすぎた不思議な縁ではないですか。
かつて家内に桂馬の詰め合わせを初めて見た時、「尾道では、こういうのも天ぷらと言うの?」と聞きましたが、
それを聞いた時、先に食べたのが桂馬の天ぷらだった私は、後に普通の天ぷらを知った時に「こういうのも天ぷらというのだ」と、
逆に思ったことを思い出しました。
両親は亡くなり、墓は兄の住む鎌倉にでき、生家は他人の手に渡り、尾道との縁も薄れてきたのですが、桂馬との縁がきっかけで、
どんどん蘇っていくようで、ありがたいことだと感謝しています。
|